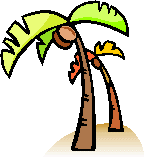|
~ スポーツから見るフィリピン ~
裕福層に属するフィリピン人は,全人口のわずか2%ほどで,さらに皮肉なことに,
その2%の裕福層が国内の富の約8割を独占している。このようなフィリピン社会
の中で,スポーツと社会のかかわりについて,現地調査をもとに考察していく。
フィリピンではバスケットボール,ボクシング,ビリヤード,ボーリングが人気のある
スポーツだが,身近にプレーをする (体を動かす) という点では,バスケットボール
のみといっても過言ではない。
どのバランガイ (最小行政単位) にも大きさや質の差はあれ,バスケットゴールと
コートがあり,少年・青年たちは入れ替わり立ち代わり,バスケをしている。
バスケのゲームに参加させてもらう機会を得たが,チーム編成は近所の暇な青年
たちで構成され,1ゲームごとにチーム,ならびにプレーヤーを入れ替える形式で
あった。 ルールについては,細かい部分までは気にせず,楽しみながらゲームを
行うとことが優先される。
ゲームには現金が賭けられているため,勝ち(パナロ),負け(タロ)の叫びと共に
活気に拍車がかかる。 もちろん,賭けのないゲームも頻繁に行われる。
彼らの中には麻薬常用者,前科のある者,朝から晩まで賭け事をして過ごす者も
少なくなく,実にさまざまだ。
有名選手として活躍することを夢見る者もいるが,大多数は,娯楽の一環として,
バスケに興じているようである。日本で散見されるようなスポーツ概念や健康維持
のためにスポーツをするという考え方は,あまり浸透していない。
まず,フィリピンにおいて,何らかのスポーツを続ける環境にある者は,裕福な者
に限られているということが,第一に挙げられる。
裕福層に属するフィリピン人は,国技であるバスケについて,興味を示し,テレビ
中継など熱心に見たり,実際にプレーをすることもあるが,男女を問わず,ゴルフ,
スキューバダイビング,フィットネスジム,テニスなど,エグゼクティブなイメージを
連想させるスポーツを健康維持の一環,または,趣味として楽しんでいる。
庶民レベルでは,男性については先述したように,バスケをすることで体を動かす
機会を得ているが,女性については,スポーツをする機会は無いに等しい状況で,
小学校,高校で体育をするのみという現状である。 しかも,その体育の授業という
のは,体を動かして汗をかくというものではない。
フィリピンの公立学校の場合を例に挙げると,週に60~90分程度,カリキュラム
を消化することを優先する形で,バレーボールごっこをしたり,ダンスをしたりする
程度の体育であるため,日本の体育の授業とは大きく異なる。
そして,学校を卒業すれば,女性の場合,スポーツをする機会は,さらになくなり,
その機会に恵まれないという構図が出来上がっている。
国外からは,教育熱心と評価されているフィリピンだが,果たしてどうであろうか。
公立学校 (小学校6年制,高校4年制が義務教育) の授業料は無料であるが,
実情は制服代,教材代,雑費が自己負担となるため,高校卒業まで至る割合は
決して高いとはいえない状況である。また,財政難で教師,教室,教材が不足(1)
しており,児童・生徒は,午前組と午後組に分かれ,入れ替え制で通学している。
教師の賃金も安いため,教師を辞めて肉体労働者・家政婦として,海外に出稼ぎ
に行ってしまうケースも珍しくなく,悪循環が存在する。
教育においても貧富の差が露呈し,卒業後の進路や就職に至るまで,その格差
やコネが付きまとっていることが散見できる。
近年においては,政府公的機関のみならず,市民団体などによって,スポーツを
含めた教育振興、国際交流が盛んに行われるようになってきたが,国家の政策に
関わる領域や事柄も多く存在するため,一筋縄にはいかないことが見受けられる。
スポーツ観戦という,娯楽としてのスポーツだけではなく,より多くのフィリピン国民
にスポーツをする楽しさをはじめ,また,意外なほど身近に出来ること,健康に良い
ということを広める努力を熱心に行うべきではないだろうか。
少しの距離でも歩くことを嫌がり,運動不足による肥満が多いフィリピン。
スポーツといわないまでも,体を動かすことの大切さをより多くの人々の間に浸透
させ,定着させることは,健康維持・病気予防の観点からも,大きな意義がある。
脚 注 (1)
2004年12月,公立小学校で8年間使用されていた歴史社会科の教科書に
ついて,約800箇所の訂正箇所が見つかった。
「日本の首都トウキョウは昔,キョウトと呼ばれていた」,「万里の長城の長さは
270kmである」,「第2次世界大戦時に,ユダヤ人は大量虐殺を行ったことが
原因で,現在も世界で差別されている」 など驚くべき内容であった。
教育大臣は教科書検定システムを抜本的に見直す約束をしたが,割当てられ
る具体的な数字 (予算)についてのコメントはされていない。
<参考文献> 平井肇著 『スポーツで読むアジア』 (世界思想社2003年)
<調査協力者> A.アルカレス氏 (Lyceum大学教員),Far East大学の学生さん,
マニラキアポ地区の無職のバスケ好き青年,働き者の女性
|