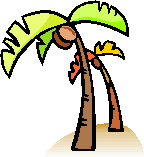〜 取引コストの経済学において取引形態はいかに形成されるか 〜
市場か組織かという選択を決めるのは,「取引コスト」 といわれるが,取引コストの
経済学では,取引コスト (お金・時間・リスク) は小さい方が好ましく,それが組織
取引であっても,市場取引であっても,低い方を選択すると考えられている。
(コース,および,ウィリアムソンの取引コスト理論)
人間は不完全であるため,取引コストが大きくなれば,市場取引ではなく組織取引
を選択し,取引の内部化 (垂直統合) を行って,優位性を獲得しようとする。
ここでいう人間の不完全性とは,人間は機会主義的な行動を取ったり,情報収集・
処理能力が不完全であることを指す。
組織取引 (垂直的取引・内部取引) において,お互いが満足できるような取引が
長期にわたり繰り返し行われる場合には,信頼関係から,裏切行為を回避できる
可能性が高くなるだけでなく,協働や企業間調整が行いやすい。 しかし,業務を
うまく結合出来ない場合や甘えなどが横行する場合は,組織取引においても取引
コストは高くなると同時に,官僚主義的要素が強くなるなど,組織の硬直化・肥大
化を招く可能性が高くなる。
これまでの自動車メーカーに見られる自動車販売会社と部品供給会社は垂直的
な統合の典型例であり,企業は販売や生産について,自社のコントロール範囲を
拡大すると同時に,一本化が容易に行えるため,経営効率を上げることができる。
しかし,近年のルノーと日産の自動車メーカーの連合は水平的分業であり,企業
の規模の拡大を実現し,市場における自社の影響力を拡大した。
情報化社会といわれる昨今は,水平分業が多く見られるようになり,その内容や
範囲は多岐にわたり,企業が掲げる目標によって,戦略も多様化している。
グローバル展開する企業は,世界各国に事業所を設け,事業所間で取引 (内部
取引) を盛んに行っている。 それは内部取引のほうが有利であると判断したため
であるが,決して,内部取引だけを行おうとしているのではなく,現地企業との取引
(市場取引) を行うほうが有利だと判断すれば,積極的に採用している。
ライセンス契約を結んで技術提供をするケースなど,今後も増加すると思われる。
そして,インターネットの普及によって,取引コストが低下しているため,組織取引
の優位性が必ずしも高いとは言えなくなっており,まさにケースバイケースである。
しかし,取引コストの経済学でいう,取引コストがゼロになるとは考えられず,あく
までもゼロに近づくに過ぎないため,問屋無用論については異議を唱えたい。
さまざまな取引をするにあたり,消費者のニーズを的確に捉え,迅速性・効率性を
伴う流通システムを構築し,且つ,健全な取引を行うことが求められる。
それと同時に,柔軟性のある経営ノウハウを持つことが重要で,それが欠如して
いる場合は,生き残りは困難で淘汰されるであろう。
これまでは,プッシュ理論が主流であったが,今後は,ますます,プル理論も同様
に重視され,情報のシェアが不可欠となるが,アウトソーシング等で本体を可能な
限りスリム化する傾向にあっても内部取引が消滅することはないので,内部取引
のコストについても,削減する努力は継続されるであろう。
このように,垂直的システム・水平的システム,共に一長一短であるため,どちら
が良いかは一概にいえないが,今後の取引形態や流通システムは,情報のやり
取りを軸として,水平的なものにウエイトを置く形で,形成されるのではないかと考
えている。
|