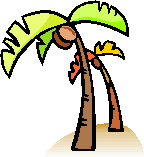~ 「ドル本位制」 の存立根拠とその積極的意識と問題点 ~
1944年、国際通貨制度の再構築や自由貿易の促進などを取り決めた国際通貨
基金協定が結ばれ、国際通貨基金 (IMF)と国際復興開発銀行 (IBRD)が設立
された。 圧倒的な経済力を持っていたアメリカには世界の金が集中しており、アメ
リカの金をもとに発行されたドルには 金と同様の価値があった。
アメリカが外国通貨当局に対して、一定価格で金の交換に応じる代わりに、外国
為替市場への介入を免除されたことと、他国に公的資金を供与することで他国の
対ドル平価の維持を支えた。
このように、ドルと各国通貨の価値を連動させたことから、金為替本位制としての
ドル本位制が確立した。
この制度では為替相場は固定されていたが、ベトナム戦争での大量支出や軍事
力の対外増強などを行った結果、アメリカは巨大な財政赤字を抱え、大量のドル
が海外に流出。 その結果、金の準備量を超えるドル紙幣の発行を余儀なくされ、
金との交換を保証できなくなったため、1971年8月、ニクソンはドルと金の交換
停止を発表。(ニクソン・ショック)
これにより、IMF体制は崩壊し、1973年、国際通貨制度は固定相場制から変動
相場制に移行した。 変動相場制におけるドルの存立は、ドルの弱さを示している
のである。とは言え、ドルは資金循環構造に基づき、世界の基軸通貨として世界
金融の中心的役割を現在も担っている。
基軸通貨であるが故、海外から資本が流入し、それにより金利を低く抑えること
ができ、財政赤字が膨らんでも 国債発行コストを抑えることができるだけでなく、
インフレ、デフレの輸出も可能となる。
問題点は、アメリカへは安定的な資金が流入しているにもかかわらず、アメリカに
よる投資が短期的で流動的であるため、投資相手国はリスクに晒される。
それだけでなく、アメリカが 為替相場の変動を避ける金融政策や、外国為替市場
への介入政策などを行うと、他国の経済は振り回される。
日本のバブル崩壊、アジア通貨危機などにも、その一端は見て取れる。
また、他国からの資金流入が将来にわたり、安定的、且つ、継続的に行なわれる
かどうか保証はないため、魅力的なドルであり続けるために、金利や相場を高め
に設定 ・維持しなければならないのだが、それに対して 不信感が広まった場合、
ドルは暴落し、世界規模で経済混乱が発生する危険性がある。
今後、ドルと並行して、ユーロが2大基軸通貨として 機能を果たすようになれば、
リスク回避 ・分散という側面で、大きな意味を成すが、ユーロ通貨圏が拡大傾向
にある中、加盟国間の経済格差をはじめ、懸念材料が多い。
何より、EUの主要国である、ドイツとフランスが、EU加盟に際するルール (財政
赤字はGDP比3%以内) を守れていないため、基軸通貨としてのユーロの存立、
及び、先行きの不透明感は拭えない。
|